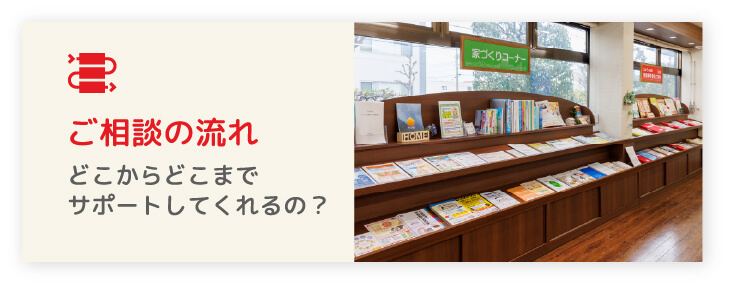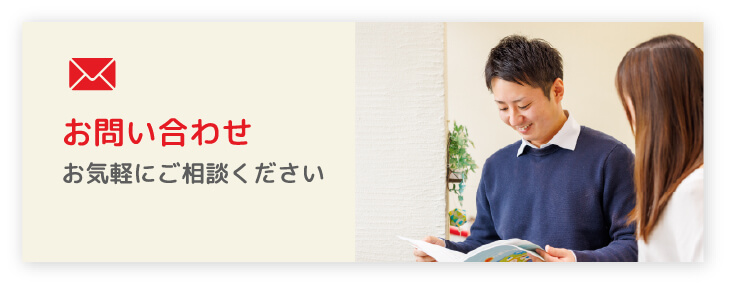前回、2025年4月からの建築基準法の改正(省エネルギー対策)についてお話しました。引き続き今回も建築基準法に関する話題にしたいと思います。
法改正には2つの目標が定められているとお伝えした内容のうち、今回は「木材利用の促進」に関連するものになります。
木材利用の促進という大枠のうちのほんの一部でしかないのですが、家を建てようとする皆さんにとっては、とても重要だと思われる、構造の部分、構造の安全性の基準が見直されたというお話です。
「構造の安全性」は、わかりやすくいえば、地震に強い家にするための基準(それだけではないですが)という説明ができます。
いつ起きるかわからない地震、でも、いつか起きた時のことを想像すれば、「耐震性能の高い家」にしたいと思うのではないでしょうか。今回はその基準、計算方法が見直されたというお話ですが、難し話をできるだけ平易にわかりやすく、イメージしてもらえるように書いていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
「構造の安全性」とは
構造について
構造の安全性の話の前に、まず、構造とは何かをお伝えしましょう。じゅうmadoでは、建築関係の方以外にお話することが多いので、分かっているよという方は、読み飛ばしてください。
構造とは、家の骨組みの部分とよく言われます。家を建てるときに使われている、柱や梁、土台、雨風をしのぐ屋根や壁。建物を支える基礎、普段過ごす部屋の床や天井、さあ、あなたが、すぐに分かる用語はどれでしょう?そして、構造とはどの部分でしょう?
構造のことを骨組みの部分と、私達はよく表現するのですが、骨組みってよく考えたら何だろう?というそもそもの疑問から。
骨は、もちろん分かりますよね。私達の体にある骨。私達の体を支える大事な部分です。私達は骨がなければ、しっかり立つことは出来ないでしょう。
同様に、家などの建物が、しっかり建っているために必要な部分があります。そういう意味で、家の骨組みと表現するんでしょうね。
それを建築用語では「構造」と言われるのです。ただ、人体の骨のように、これが構造と明確に分類されてはいません。人によって多少異なる部分を含めて構造と表現するケースもありますが、先ほどの用語の中でいえば、土台・柱・梁。これらは、構造部分になります。
これは木造建築の場合は、木材でできています。この木材の組み方をみると、家の形はわかりますよね。この構造部分に、様々な材料を施して家が出来上がっていく。人で言うと筋肉や皮膚のようなものでしょうか、そう考えると、大きな骨、骨格部分が構造といえそうですね。そして、他にもいろいろな小さな骨にあたる部分と一緒にしっかり全体を支え合うように出来ているのが木造建築のすごさです。
木材は、土台・柱・梁以外にもたくさん使われています。最初の用語にあえて書かなかった、棟、母屋、束、筋交い、など。それぞれが、それぞれの部分で大切な役割をはたしています。
そして、この本体をしっかり支えるために、鉄筋コンクリートで作られている基礎の部分があります。
安全性について
構造って何?がイメージできたところで、その安全性。安全である基準とはどういうことかを、わかりやすく説明するとすれば、地震や台風、雪などの自然現象に対して、ある程度は安全を確保しておこうという基準です。安全に暮らすためには、このような対策をするべきですよね。
では、安全を確保するために、どういう基準があるかということを、ざっくりとお話しておきますね。
地震に強い家とよく表現されていますが、どういう家が地震に強いとされているのか?どういう計算をしているのか。
また難しい話になりそうなので、計算は設計士に任せるとして、イメージだけつかんでみましょう。
先ほどの構造、骨組の部分をまずは丈夫にするということです。想像してみてください。「丈夫な骨」骨が太ければ太いほど丈夫そうだな。と思いませんか?昔の大きなお寺などを見に行けば、びっくりするほど、大きな柱や梁が使われています。見るからに、スゴイ!となります。
大きな建造物だからこそ、あのような骨組みなわけですが、住宅ではどうでしょう。住宅でも、材料の大きさは違えど、柱や梁が、建物を支える役割をしています。お寺のような大きな柱や梁は不要だとして、ではどのぐらいの大きさなら良いのでしょうか?同じ太さでも、長さが長くなれば弱くなりそうです。ある程度は想像できるでしょうか。
例えば、住宅で使われる標準的な柱の太さは決まっています。柱を太くすれば丈夫になりそうですが、その分、壁の厚みが厚くなり部屋が狭くなることになります。では、太さを変えずに、家全体を丈夫にするにはどうしたらよいのでしょうか?もちろん、ちゃんと計算方法があります。
家は、建物(構造)全体で丈夫さを担保するようにできています。これをまずは理解するとよいです。
丈夫にするための計算方法では、地域を考慮するようにもなっており、地震係数・風圧係数など称される係数によって区分けされています。ご自身が住んでいる地域によって、必要な丈夫さは計算すると違うということでもあります。雪が多いところでは、多雪地域として考慮され、そのような環境下で耐えうるように、計算の根拠はつくられています。
建築したい家が、構造的に大丈夫かどうかを計算するということは、あらかじめ定められた基準値をクリアできるかどうかということです。
そして、基準値をクリアしていない家は建ててはいけませんよ。ということになってるということですね。その基準値の考え方が変わるのが、法改正となります。ではなぜ基準値を変える必要があったのか、次の項目で説明しましょう。
計算による検討
基準値を現在の状況に合わせる
基準値を変える法改正は、なぜ行う必要があるのでしょうか。そして、今までに建てた家は、どうなのだろう?という心配がでてきませんか?
残念ながら、昔の造りの家はやはり弱い部分があるところは否めないと思います。
災害となるような大きな地震がおきた場所で、不幸にも倒壊した家は、構造的にこういう問題があったと指摘されていることがあります。このような問題を把握し、改善していく、これが基準の見直しです。
耐震性だけに関していえば、2000年にも法改正をされており、通称2000年基準などと言われています。その当時の改正の内容をベースに、今回さらに強化されているということになります。具体的な計算方法を一部変えたり、チェックすべき項目を増やしたりすることで、より安全を確保できるように基準が再設定されたのです。
壁量計算の変更
少しだけお話すると、壁量計算という計算方法があり、耐力(地震時に耐える力があるかどうか)を算定していますが、改正前の計算方法では屋根が瓦屋根なら重い屋根、板金などの場合は軽い屋根という大雑把な分け方でした。しかし近年、屋根の上に太陽光パネルを載せたりするケースが増えたことで、実際の荷重はどうなんだろう?という問題が出て来たのです。屋根だけではなくて、外壁材も種類が増えたことで、実際の荷重に即しているかどうか検討しなおされました。
法律的には、建築基準法の改正に伴い、建てることができる基準を上回ることが必須になり、家を建てる際に必要なお金は高額になってきます。また、法改正以前の建物でも、既にその改正後の基準を上回るような住宅もありますので、ご自身の住宅が法改正前に建てられていたから弱いということでもありませんのでその点、誤解されないでくださいね。
柱の重要性
計算についてもう少し深くお話すると、先に述べた「荷重」は重要で、例えば屋根が重いほうが、地震が起きた際に揺れが大きくなります。イメージはしやすいですよね。人の場合も、頭の上に重い物をもっていれば、不安定になりますよね。片手だけで、重い物を持っていたとしても不安定になりやすい、その不安定な状態をつくらないように構造計画を立てることが重要です。
ただ、構造は住む人には見えない。体の中の骨が見えないのと同じ。だから、分かりにくいし、見た目(住み心地や表面の仕上げ材)に、通常は意識がいきがちです。生活のしやすさ、間取りを優先したら、構造的に弱い部分が出てくるかもしれないと、ちょっと心の片隅にでもおいておきましょう。
そして、設計士に計算をしてもらうことで、構造的に問題がある箇所が見つかったら、その理由を確認して対処法を検討しましょう。もしかしたら、生活動線を考えたら、できれば無い方がいいなと思う場所に、柱が必要だと言われるかもしれません。
柱があることにより丈夫になるということであれば、柱を優先してはいかがでしょう。仮に、大きな空間が欲しい。どうしても、柱や壁があると嫌だと思う場合は、そのための別の方法を検討することにはなりますが、その場合は、価格的には高くなると考えた方がよいです。
構造計算をする。家全体が構造的に丈夫になる。これは、柱の問題だけでなく、他の箇所との関連も重要になります。材料が変われば、荷重も変わります。支える柱がないということは、どういうことか想像がつきますか?
柱がないまま、建物の強度を確保しようとしたとき、上の梁の材料が大きくなることが一般的です。大きくなった梁を少ない柱で支える必要があるのです。
柱を1本減らす分、他の柱が頑張らないといけないってことですよね。
仮にその柱1本では、無理、支えられないとなったなった場合には、今度は柱を大きくしたりします。大きくしないと、支えられないからです。
そんな計算方法が、新たなチェック項目に加わった改正になります。もう少し詳しく説明すると、簡易的なチェック方法が用意されていて、この方法を使う場合は、上部の梁の大きさまでは検討しません。どういうことかというと、当然大きくて丈夫な梁にするだろうという前提で、必要な柱サイズが決まるようになっています。
許容応力度計算
詳しい計算方法では、許容応力度計算という計算を行いますが、壁量計算やチェック法などは、この計算を元に考えだされた簡易的な方法と捉えられると良いかと思います。では、許容応力度計算では何をしているのかというと、強い地震による揺れがきたときにどういう力が加わり、どう耐えるか(許容できるか)を計算により求めているのです。
この場合は、上部の梁の大きさや強度がどれ程であれば、大丈夫かもわかりますし、さらにその下にある柱に、どれほどの力が加わるか、そしてどうすれば耐えられるかがわかります。材料ひとつひとつ、最初にお伝えした、木組みの仕方によっても変わるという力の加わり方を、構造部分、1つ1つ、確認する方法になります。
ただし、この許容応力度計算は、先ほどお伝えしたように、すべての材料1本1本にどのような力が加わるかを検討するため、材料がひとつ変わっても全ての計算をしなおさないといけません。
最初に説明した通り、構造は多くの材料で支え合い、建物全体をしっかり丈夫にするものです。何かひとつでも変われば、そのバランスが変わってしまい、他の部分にも影響が出るのです。だから簡単に説明できるお話ではないのですが、イメージだけでも掴んでおいてもらえると、きっと家を建てる時には役立つと思います。
あなたにとって、優先すべきは何か、法律を守らないといけないのは当然ではありますが、それを守った上で、もっと丈夫な家づくりを希望するのか。耐震等級1,2,3などの等級区分があると聞いたことがあれば、わかりやすいかもしれませんね。もっと丈夫な家づくり、計画段階で念頭においておくと良いでしょう。
今回は、耐震等級のお話まではできませんが、また、いつか機会があればお話したいと思います。
(じゅうmado宇部 川村菜穂子)