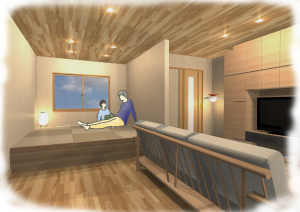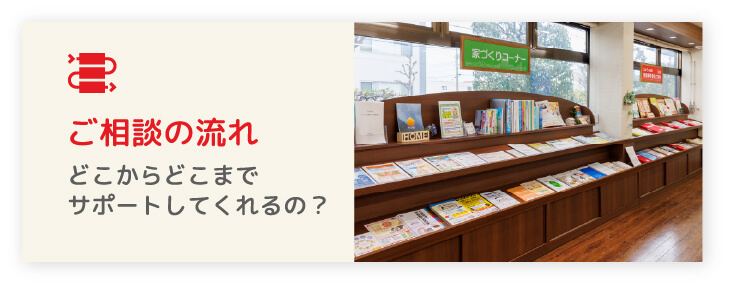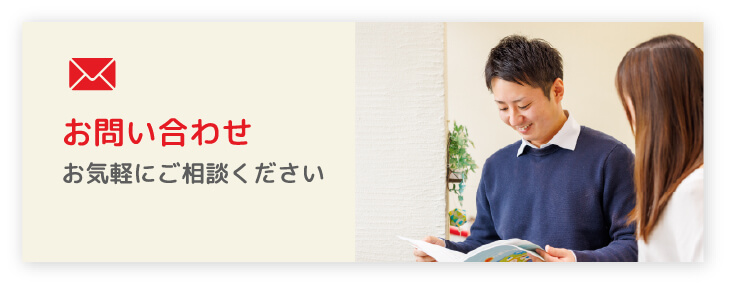今回のテーマは調湿効果!家に使われる材料は様々ありますが、自然素材が良いのか、新建材が良いのか。そもそもの違いは何なのか。普段聞きなれない言葉が並ぶ、家づくりの打ち合わせ。
本格的な家づくりの打ち合わせに入る前に、様々なことを学んでおくことで、建築会社との話もスムーズに進み、失敗もしにくくなります。
こだわりを実現したい人にこそ、メリットデメリットを知った上で、選択して欲しいと思います!そんな思いを胸に、お伝えする本日のテーマは、調湿効果についてです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
そもそも調湿効果とは何か
調湿とは、文字のごとく、湿度を調整するということです。もう少し、具体的にお伝えすると、湿気が高い時には水分を吸収して、抱え込み、乾燥している時には、もっている水分を放出する、これにより、空間を快適に、過ごしやすくするということです。
調湿効果がある素材、材料、建材、などと言いますが、これらの材料を使うことで、何故そんなことができるんだろうか?と考えたことありますか?
私自身、言葉の通り、調湿効果、調湿作用ということを口にすることがよくあるのですが、そして、そのことが健康な暮らし、快適な暮らしに結びつくイメージはできるのですが、その作用そのものは、目には見えないことなので、よくよく考えたら、よくわからないなと。思ったりします。
快適に過ごすことができる、室内の湿度は、40%~60%ぐらいと言われ、加湿器や除湿器を活用することも当たり前のようにもなってきました。
つまり、湿度が高くても、低くても、不快感を感じるという、感覚はなんとなく皆さんもわかると思います。また、そこで暮らしている人間のためだけでなく、家そのものの健康ということにも、湿度は大きくかかわってきます。
湿気が多すぎると、木が腐ったり、しろありの被害に合いやすい、当然、家にとっても良くない状況であることは、容易に想像ができます。
調湿作用が何故働くのか
ここでは、どうして、調湿作用が働くのかを先にお伝えします。機能や機構的なことに、そこまで、興味はないよっていう方は、読み飛ばしてくださいね!
調湿効果を持つ材料には、下記のような仕組みがあります
① 多孔質構造を持っている
吸湿性を持つ、自然素材のひとつの特徴としては「多孔質(たこうしつ)」という、無数の小さな穴(孔)がある構造をしているということです。
孔があいていることで、空気中の水分を吸収・保持し、必要に応じて放出することで、室内の湿度を一定に保とうとする働きをします。イメージしやすいように説明すると、この 多孔質構造とは、“スポンジ”のようなもの。スポンジって、ぎゅーってしぼると水がいっぱいでてくる状態だったとして、しぼる前は、ある程度水を保持しているから・・押さえたときに、出てくるわけですよね。
それができるのは、たくさんの穴があいているからということなんです。穴が大きめでわかるスポンジもあれば、小さくて、ほぼわからないスポンジもあると思いますけど、水があるところに乾いたスポンジを置くだけで、スポンジは水を吸収しますよね。
湿度が高い室内では、空気中にある余分な水分子が、この穴に吸着される。だから、そういう多孔質構造を持つものが、調湿性のある材料というわけです。
②繊維(セルロース)
先ほどの多孔質の特徴と、区分して、繊維質な材料を特徴的なものとして取り上げます。代表されるのが木材です。木材の繊維(細胞)には、水分が保持されています。よく、木は呼吸しているという言い方をしますが、吸放湿するこの作用を表す言葉としても使われていて、生きているという感じがよく伝わりますよね。木材は、水分を吸収したり排出したりすることで、室内環境を整えてくれるため、積極的に利用されています。
木は、この繊維や水分を運ぶための導管があることで、吸放出をしています。吸湿することで、木材そのものが膨らみ、排出、乾燥することで、木材が縮むという現象、聞いたことがある人も多いと思います。
空気中の水分(湿気)は、とても小さな粒(分子)でできているので、目にはもちろん見えませんし、空気中を自由に動いています。そのため、部屋全体の 湿度が低くなってくると、たまっていた水分子が、水分の少ない場所へ移動する(外に出ていく)のです。
空気が乾燥すると、孔の中にある水分の方が空気中より多くなるため、濃度の差(湿度のバランス)を埋めようとして水分子が外に出る、この自然な動きこそが、調湿作用ということになります。
調湿作用がある建築材料
基本的に、自然なままの状態に近い方が、調湿作用は高まります。吸放湿性を持つのは自然の中で呼吸していた素材や、湿度に適応していた素材が多く、自然由来の繊維や鉱物を原料にしているものです。
化学処理が少ないほど性能が発揮されやすく、加工の過程で防水処理やコーティングがされてしまうと、本来の吸放湿性は失われていきます。
現在、調湿効果を謳っている材料としては、下記のようなものがあります。
自然素材
ここでは、建築材料として利用される機会が増えた「自然素材由来」の材料、その特徴をお話します。
珪藻土(けいそうど)
微細な孔が非常に多く、高い吸放湿性を持つことで知られており、最近では、壁の仕上げ材に利用したいという人が増えています。吸湿性のほかに、消臭効果もあるため、その特徴を活かして活用すると良いですね。
ちなにみ、珪藻土は、植物プランクトン(珪藻)の殻が化石化した固まり(地層)で、非常にやわらかく、手で簡単にくずれるようなものです。
この珪藻土を室内の壁に利用する場合には、固まる必要があるため、利用している糊・硬化材によって特徴が異なってきます、つまり、販売されている商品ごとに成分が異なるのです。
自然なままの状態に近い方が、調湿作用は高まりますが、実際の作業性や耐久性などを考慮の上、商品化されているので、その加工過程で、吸放湿性がどの程度発揮できるか、あるいは、どの程度失われているかが、異なってくるということです。
また、珪藻土は次項のしっくいに比べ、より多くの水分を保つことができる構造をしています。そのため、調湿性能という点では、珪藻土の方が優れています。
しかし、水分を多く保つことで、カビが生える原因にもなるということなので、あまりに、湿気・水分が多いところでの使用には注意が必要です。
漆喰(しっくい)
珪藻土とよく比較される、調湿作用がある素材として、しっくいがあります。しっくいは、調湿効果だけでなく防カビ・抗菌性もある素材です。
調湿作用は、珪藻土と同じ、多孔性をもっていることによりますが、防カビ・抗菌作用は、しっくいの主成分が、消石灰(しょうせっかい:石灰石を焼いて水と反応させたもの)であるためです。
石灰は強アルカリ性で、殺菌効果があるとされていますので、この点が、珪藻土より優れているともいえます。
しっくいは、昔の家の外壁に使われており、現在でも、白壁の街並みなど、目にする機会があると思います。真っ白の壁、屋根瓦の間にも使われていますね。固まると、しっかり固く、不燃性もあり、風化もしにくいため、外壁に使われていました。
最近はDIYで使用したり、室内の壁に使用したり、その用途も多様化してきました。そのため、最初から室内用のかべ材として販売されている商品もあります。色にしても、しっくり=白色ではなく、デザイン性を求めて、色が選択できるようにもなりました。
ただ、やはり、着色の為に混ぜられている化学物質があるとすれば、自然由来のしっくいといえど、その性質は異なるものになっているかもしれません。商品を選ぶ際には、材料、成分などをしっかり確認しながら、作業性なのかデザイン性なのか、何を優先するかによって選択して欲しいと思います。
また、調湿性という意味でいうと、珪藻土と比較して、より吸湿効果が高いのは、珪藻土の方です。しっくいの特徴である、防カビ・抗菌性を必要とするかどうかを選択のポイントとしてみてはいかがでしょうか。
木材
木の繊維が湿気を吸収・放出します。自然の木ということで、当然、その種類(樹種)によって性能は異なりますが、大まかに針葉樹と広葉樹に分けて、お伝えします。
スギやヒノキに代表される針葉樹は、住宅でたくさん使われていますので、聞いたことがある人も多いかと思います。自然素材のある暮らしを好む人には、人気のある木材です。
木の特徴としては、広葉樹に比べ、繊維が細く、導管も細いため、吸湿のスピードがゆっくりになります。保湿力という部分でも、少なくはなりますが、その他の特徴を考慮して、選択すると良いでしょう。
例えば、木材が仕上げに使われている場所として、床がありますが、針葉樹は、柔らかいことも特徴のため、傷がつきやすいのですが、その分、足触りが良くなります。
逆に広葉樹は、水分を早く多く吸収することができ、時期や使い方によって、急に湿気がこもりやすくなるような場所に利用すると良いでしょう。
広葉樹は固い木であることが多いため、触れ心地という点では、若干劣るかもしれません。心地に関しては、人それぞれの感じ方であるため、どの程度の差を感じるかは、明確にはお伝えできませんが、ひとつの特徴として知っておいて良いと思います。
いずれの場合も、木の持つ、調湿効果をうまく利用すれば、例えば、傷がついた場合でも、水を含ませることで、木材が膨れ、傷が目立たなくなることもあります。
逆に水分が浸みこむため、汚れやすく、シミ残りが気になることもあります。
天然木材(無垢材)は、硬化剤・粘剤などを必要とする珪藻土やしっくいとは違って、糊付けなどしない場合は、自然そのものであるため、メンテナンスを行うことができれば、非常に長く使え、経年変化も楽しむことができる素材です。
調湿効果を活かして、押し入れなどの湿気のこもりやすい場所の壁や天井に木板を張るという選択をされる方も多いです。デザイン性よりも機能重視のところでは、節が多くある、色味がバラバラだったとしても、気にならないですしね。
また、作業性や耐久性、デザイン性を考えて、木材にも加工を施す場合があります。例えば、表面にウレタン塗装を施すことで、表面に塗膜ができ、傷、へこみはしづらくなります。とはいえ、薄い塗膜であれば、やはり重たいものを落としたりすれば、傷もつきますし、へこみもします。傷や凹みができると、自然素材と違って、回復させることが難しく、かえって痛みが進行しやすいともいえます。
新建材
ここでは、自然素材ではなく、自然素材のその特徴を研究して真似をして作り出された新しい素材、新建材についてお伝えしたいと思います。
※新建材とは特別に何のことを差すという明確な分類はありませんが、新しい技術を組み込んで、昔ながらの建築材料とは異なる新しい建築材料という意味で一般的に使われている言葉です。
エコカラット
自然素材の多孔性という特徴に注目して開発された商品です。デザイン性が高く、機能的な面はプラスαぐらに考えている人もいるぐらい人気があります。住宅の壁、全てを、調湿できないビニールクロス貼りにするのではなく、部分的に使用する例も多くあります。お洒落な空間を創ると同時に、吸湿効果があるのは嬉しいですよね。
珪藻土などの自然素材の話を先にしましたが、自然素材の特質を真似しているということもあり、その品質は安定しており、一定の効果があることは、実験などで証明されているので、興味のある方は、メーカーのサイトなどで、詳細を確認してみてくださいね。
では、珪藻土とエコカラットどっちがいい?と迷う方も出てくるかもしれません。珪藻土として販売されている商品も、加工の過程で、合成樹脂や接着剤が混ざることで、本来の珪藻土が持つ力を発揮できていない、調湿性が弱まっていることもありますし、珪藻土を塗る壁の厚みなどによっても、その効果は変わってくるでしょう。
そのため、単純に比較することも難しいとは思います。調湿性を求めつつ、やはり家として、部屋としての空間の在り方(見た目・デザイン)によって決めるという方も多くいますので、壁がどんな風に仕上がるのか、を確認して決めるというのもひとつの方法かもしれませんね。
さらりあ~と
こちらの商品は、エコカラットに比べれば、タイル貼りのようなデザイン性はありませんが、シンプルに性能を求める場合は、検討してもよいかもしれません。比較的、自然素材の珪藻土やしっくいで仕上げるときのイメージに近い新建材だと思います。
珪藻土やしっくいのような自然素材であれば、職人の技術により、壁に模様を付けたりすることができます。しかし、職人の手によってつくられるため、その見た目は、出来上がってみないとわからない、変わる可能性もあります。その点、建材としてメーカーが商品化しているものであれば、加工しやすい、施工しやすい、品質が安定している、施工事例の写真などで想像した通りに仕上がりと思います。
ハイクリーンスカットボード
これは、仕上げの材料ではなく、調湿機能タイプという石膏ボードになります。最近の住宅は、ほとんどが、石膏ボード貼りであり、木材の下地は少なくなっています。
石膏ボードは、耐火性があるため、火災時の炎症を防ぐという意味では有効であり、価格の面、施工のしやすさからも、多く利用されています。
この石膏ボードの上に、珪藻土を塗ったとしても、あまり調湿効果が発揮できないと言われています。それは、単純に珪藻土を使う量の問題であり、仕上げのための非常に薄い塗り厚でしかないからにほかなりません。
せっかく珪藻土を利用するのであれば、下地にも、自然素材を使いたい、しかし昔ながらの土壁を新たに施工するというのはさすがにちょっと、時間もかかるし、お金もかかるし難しいというのが現実です。
そんな時には、この調湿機能をもった石膏ボードを利用するというのもひとつの方法かもしれません。その場合、通気性のあるクロスや水性ペイントで仕上げることが多いようです。
なお、この石膏ボードをそのまま仕上げ材として使うために、化粧仕上げされている商品で、ハイクリーンスカットボード押入ボードというものもあります。この押し入れボードの方が、より調湿性能が高く、こちらは調湿建材登録商品になっています。
押し入れにしか使えないわけではないでしょうが、収納スペースに、湿気取を置いている方が多くいるように、湿気がこもりやすい場所の筆頭として、クローゼット、押し入れは上げられますので、このような商品名なのかもしれませんね。
※調湿建材には、その証明としてマーク(調湿建材表示制度)があります。(一社)日本建 材・住宅設備産業協会にある調湿建材登 録・表示審査委員会が審査を行い、評価 に値するものを決定し登録します。*調湿建材表示制度とは

調湿建材表示制度で、その調湿性を知るというのも、一つの選択方法になりそうです。日本の風土に合わせた建材を利用するということは、長く住み続けるためにも、大切なことでしょう。
健康と調湿
調湿効果がある材料を、どこでどのように使用するのか、一部だけでは意味がないのか?など、いろいろ迷うことがありそうです。
自然素材を選ばれる場合、自然素材だからいいだろうと、単純に選択するのではなく、できれば、その中身まで確認しておいた方がよいということはお分かりいただけましたか?その性能は、新建材と違って、出来上がった商品ではないため、その材料の混ぜ方や配分によって変わってくるからです。
最後に、「健康」というキーワードに対する「調湿」の重要性、住まい手が感じる「快適さ」だけでなく、住宅にとっての快適さについて、もう一度お話しておきます。
湿度次第で、健康的な生活を脅かされる可能性は否めませんし、家の寿命を縮めてしまう恐れすらあります。
湿度が40%以下になるとウイルスの水分が軽くなりのエアロゾロ化が進み、空中に浮遊する飛沫の量が増えて感染リスクが高まりますし、60%を超えるとカビやダニの発生が始まり、70%以上になればシロアリにとって快適な環境が整ってしまいます。
また、木材が腐る原因となる木材腐朽菌は、大気中の湿度が高まって木材の含水率が20%を超え、気温が30℃近くになれば、繁殖が一気に進んで、家に深刻な問題をもたらしかねません。
つまり、室内で人が快適に暮らすためだけではなく、家の寿命を延ばすためにも、“調湿”はとても重要なのです。ぜひ今回の話を参考に、家づくりを検討してみてくださいね。
(じゅうmado宇部 川村菜穂子)